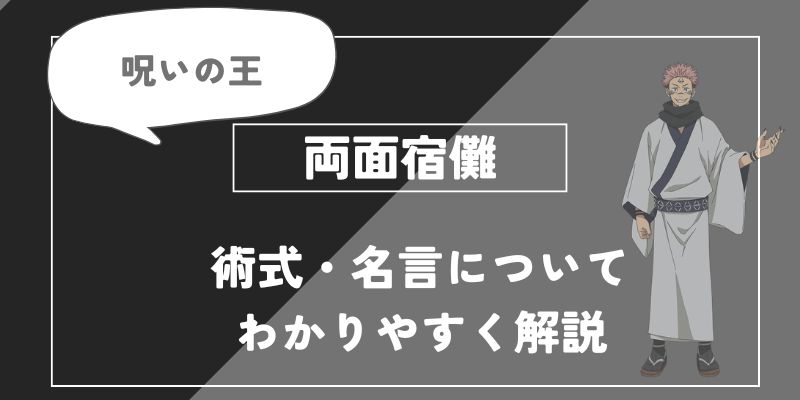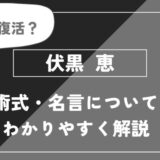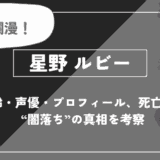この記事には広告を含む場合があります。
両面宿儺(りょうめんすくな)は、千年前に実在したとされる人間で、当時の呪術師たちをもってしても討伐しきれず、「呪いの王」として畏怖された存在でした。
死後もその強大な力は失われず、20本の指に分断されて呪物として日本各地に封印されていました。
物語は、主人公である虎杖悠仁が、偶然その指の一本を飲み込んだことから始まります。
そんな宿儺は、虎杖の内に宿ることで物語の根幹をなす存在です。
彼の存在が虎杖を巡る呪術師たちの戦いを激化させ、多くのキャラクターの運命に大きな影響を与えています。
この記事では、両面宿儺の術式・名言やエピソードなどを詳しく解説します。
\ オタクなあなたに「推すすめ」のサービス /
| 電子書籍 | VOD | フィギュア/グッズ通販 |
|---|---|---|
30日間無料 コミック.jp |  初月無料 dアニメストア |  1万円以上購入で送料無料 ホビーストック |
 6回分クーポン ebookjapan |  580円/月 ABEMA |  最大76%OFF あみあみ |
 50%還元 Amebaマンガ |  初月無料 PrimeVideo |  充実な品揃え キャラアニ.com |
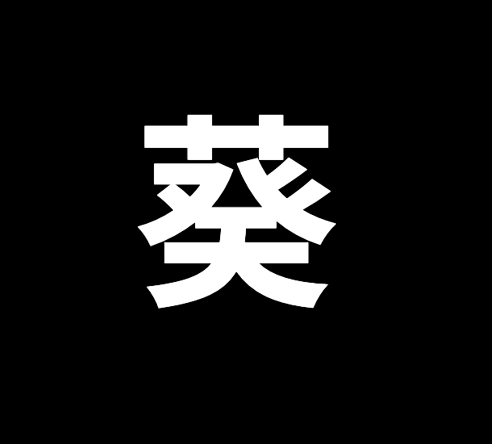
とりあえず、安いのまとめてみました!
一緒に推し活楽しみましょう…(以下より本編)
呪術廻戦アニメキャラ「両面宿儺」とは?

両面宿儺はまさに「呪いの王」と呼ぶにふさわしいキャラクターです。
その存在は作品全体の物語を動かす核であり、虎杖の運命を大きく左右します。
宿儺の性格は、その強さに比例して極めて冷酷かつ傲慢です。
他者を見下し、自身の愉悦のためならば人間であろうと呪霊であろうと、一切の躊躇なく犠牲にすることも。
目的を達成させる際にも手段を選ばず、常に虎杖の肉体を乗っ取る機会を伺い、利用できるものは徹底的に利用します。
しかも宿儺は、単なる敵役ではありません。
彼は虎杖の肉体に宿っているため、常に虎杖の精神と肉体に影響を与え、葛藤を生み出します。
宿儫の存在は呪術師たちの戦いを激化させ、多くのキャラクターの人生を大きく変えるきっかけとなるのです。
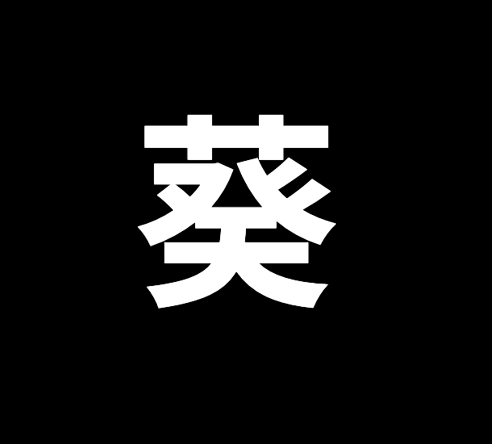
呪いの王なんて怖いよね・・・
両面宿儺のプロフィール・特徴
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 両面宿儺(りょうめんすくな) |
| 等級 | 特級呪物(特級呪術師相当) |
| 嗜好・興味 | 食べること |
| 声優 | 諏訪部順一 |
| 生得術式 | 御廚子 |
| 領域展開 | 伏魔御廚子 |
両面宿儺の目的
両面宿儺の目的は、一見するとシンプルなように見えて、その実、極めて自己中心的かつ根源的な「愉悦」の追求です。
彼は明確な最終目標を持っているというよりは、自身の絶対的な力と存在を最大限に享受することこそが行動原理となっています。
宿儺は、常に「己の力の絶対性」を証明し、それによって得られる「愉悦」を求めています。
これは、彼が「呪いの王」と呼ばれる所以であり、彼が強大な呪いの力を持つ理由です。
彼の行動は既存の秩序を破壊したり、他者を支配したりすることそのものが目的ではなく、それらの行為を通じて自身の優越性を確認し、究極の「快楽」を得ることに集約されます。
宿儺の行動には以下のような目的の裏付けがあるとされています。
・強者との対峙と蹂躙
宿儺は、自分と同等かそれ以上の力を持つ可能性のある存在、あるいは挑戦してくる存在を積極的に相手にし、それを徹底的に打ち砕くことに喜びを感じます。
五条悟との戦いはその最たる例で、宿儺は「最高の退屈しのぎ」と称し、自身の持つ全ての力を惜しみなく振るいました。
この過程で、彼は自身の術式の限界を試したり、新たな可能性を見出したりすることにも愉悦を感じているようです。
・弱者の排除と傍観
彼の視点からすれば、自分より弱い存在は価値がなく、時に鬱陶しいものです。
人間や呪霊など、多くの存在を蔑視しており、自らが気に入らなければ容赦なく排除します。
一方で、彼が直接手を下さなくても人間や呪術界が混乱し、破滅に向かう様を傍観することにも、ある種の満足感を得ているように見えます。
・「器」としての虎杖悠仁の利用
宿儺が虎杖の肉体に宿っているのは、自分の指を集めて完全に復活するためのプロセスです。
しかし、単に肉体を取り戻すだけでなく、虎杖の存在が彼の「愉悦」をさらに引き出しています。
虎杖の精神的な苦悩や葛藤、そして彼が呪いへと堕ちていく様を見届けることも、宿儺にとっては一種の娯楽なのかもしれません。
宿儺は千年前に実在したとされる人間であり、その過去には「呪いの王」としての揺るぎない地位と記憶があります。
しかし、彼は過去の栄光に固執しているというよりも、その時に得た強大な力を現代においても再現し、さらなる高みへと昇華させることに興味があるようです。
一方で、未来に対する具体的な目標や理想はほとんど見られないという一面もあります。
彼にとって未来とは、自身の「愉悦」を追求し続けるための連続した時間であり、特定の終着点は持たないのかもしれません。
宿儺は特定の思想や理念に基づいて行動するのではなく、自身の根源的な欲望に従って行動する、純粋な「悪」としての存在です。
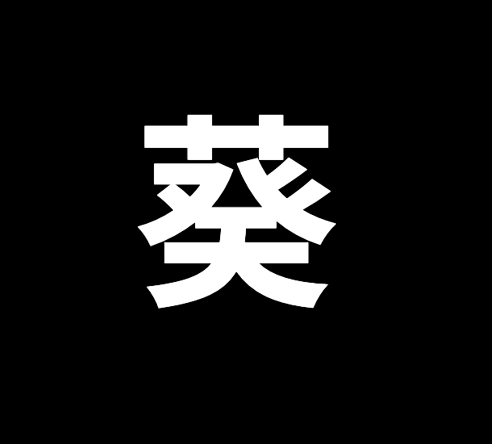
冷酷な王って感じだよね
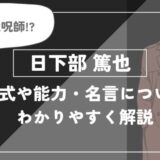 日下部篤也(くさかべ あつや)の能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
日下部篤也(くさかべ あつや)の能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 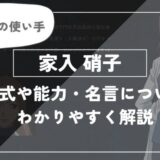 家入硝子の術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
家入硝子の術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 両面宿儺の来歴

『呪術廻戦』における両面宿儺の来歴は、その強大さから非常に謎に包まれています。
ここでは両面宿儺の来歴を紹介します。
・千年前の存在
宿儺は、約1000年前の平安時代に実在したとされる「人間」でした。
しかし、その力は当時の呪術師たちでも倒すことはできず、その結果「呪いの王」と畏怖される存在となります。
その姿は2つの顔と4本の腕を持つ異形であり、彼の強さは当時の呪術全盛期においても突出していた存在です。
原作者の芥見下々先生は、「見た目も強さも宿儺っぽいから宿儺と呼ばれていた人」と述べており、作中の宿儺は、特定の既存の伝承にそのまま基づいているわけではないと公言しています。
・死後の特級呪物化
あまりにも強大であったため、宿儺が死んだ後もその力は失われず、彼の身体は20本の指に分断され、特級呪物として日本各地に厳重に封印されました。
この指は、時が経つにつれて強力な呪いを帯び、近づくものを引き寄せ呪霊を生み出す源となります。
・虎杖悠仁への受肉
物語は、主人公である虎杖が封印されていた宿儺の指の一本を飲み込んでしまったことから始まります。
これにより宿儺の魂が虎杖の肉体に宿り、「受肉」という形で現代に復活。
この受肉は、宿儺にとっては自身の完全な復活への第一歩であり、虎杖の肉体を自身の器として利用することを目論んでいます。
・現代での暗躍と復活の企て
虎杖の肉体に宿った宿儺は、隙あらばその主導権を奪い、自身の目的(究極の愉悦の追求)のために行動します。
彼の最終的な目標は分散した全ての指を取り戻し、完全な姿で現代に復活すること、そしてその圧倒的な力をもって世界を「愉しく」することです。
作中では、五条をはじめとする現代最強の呪術師たちとも激しい戦いを繰り広げ、そのたびに規格外の強さを見せつけています。
初登場は「TVアニメ1期の第1話」※漫画では1巻の第1話
宿儺のTVアニメの初登場は1期・第1話「両面宿儺」です。
主人公の虎杖が特級呪物である宿儺の指を飲み込んでしまったことで、その魂が虎杖の肉体に宿り、本格的に物語に登場。
アニメでも同様に、第1話「両面宿儺」で初登場します。
アニメ第1話のタイトルそのものが「両面宿儺」であり、物語の冒頭で虎杖が指を飲み込み、宿儺が顕現するシーンが描かれました。
指を飲み込んだ瞬間、虎杖の身体に異変が起き、頬や体には禍々しい紋様が浮かび上がり口調も荒々しく、そして何よりもその纏う雰囲気が一変します。
そして襲いかかってきた呪霊を一瞬で「捌(はち)」という術式で切り刻み、恐るべき力を見せつけました。
アニメでは、虎杖の顔に紋様が浮かび上がる際の演出や、諏訪部順一さんの迫真の演技も相まって、宿儺の異質さと強さが際立っています。
両面宿儺の強さ
両面宿儺の強さは、「規格外」の一言に尽きます。
彼は千年以上前に実在したとされる「呪いの王」であり、その圧倒的な力は現代の呪術師たちをもってしても容易には倒せません。
作中で彼が示す能力と戦いぶりから、その強さの具体的なイメージを掘り下げていきます。
宿儺の強さの根幹にあるのは、膨大すぎる呪力量と、それを自在に操る卓越した呪力操作能力です。
宿儺の呪力量は、あの五条ですら「自分より呪力量が多い」と言ったほど。
これは並の呪術師が束になっても到底敵わない量であり、長期戦になっても呪力切れを起こす心配がありません。
さらに、ただ量が多いだけでなく、その操作は極めて精密です。
無駄なく呪力を使いこなし、術式の威力を最大限に引き出すことができます。
また、肉体強化や防御にも応用され、彼の耐久力を高めています。
複数の強力な術式もあり、それを状況に応じて使い分けることであらゆる敵に対応。
宿儺はただ呪術が強いだけでなく、肉体そのものも規格外の強さを誇ります。
虎杖の肉体を借りている状態でもその身体能力は人間を遥かに凌駕し、素手での戦闘能力も高く、驚異的なスピードとパワーで敵を圧倒します。
千年間「呪いの王」として君臨してきた経験は伊達ではありません。
あらゆる状況での戦闘を経験しており、その引き出しは現代の呪術師では考えられないほど豊富です。
冷静な状況判断力と、相手の虚を突く戦略眼は、彼の強さを一層際立たせています。
彼の存在そのものが「絶対的な壁」として描かれ、五条という現代最強の呪術師でさえ彼と対峙した際には、その限界と命を賭した戦いを強いられたほどです
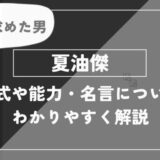 夏油傑は死亡?術式・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
夏油傑は死亡?術式・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 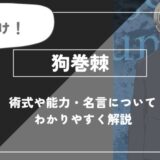 狗巻棘(いぬまきとげ)は死亡?腕は?術式「呪言」や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
狗巻棘(いぬまきとげ)は死亡?腕は?術式「呪言」や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 渋谷事変での行動
渋谷事変は、偽者の夏油傑(羂索)たちが五条を封印するために仕掛けた大規模な罠でした。
さらに、虎杖の体内にある宿儺の指を全て集め、宿儺を完全に復活させることも目論んでいたのです。
作中では、特級呪霊の漏瑚、呪詛師の枷場美々子と枷場菜々子の双子は、脹相に敗れて意識を失った虎杖に立て続けに合計11本の宿儺の指を摂取させました。
この大量摂取は肉体が呪力に適応する速度を上回り、その結果、契約(契闊)なしで宿儺が一時的に虎杖の肉体の支配権を握れるほどになったのです。
これにより虎杖の肉体の主導権を完全に掌握し、一時的ではあるものの、ほぼ完全な形で顕現した宿儺。
宿儺が顕現してからの行動は、まさに「呪いの王」そのものでした。
彼は自身の「愉悦」のために、渋谷の街とそこにいる全てを破壊します。
復活した宿儺の前に、特級呪霊の漏瑚が現れます。
漏瑚は宿儺を「呪いの王」として崇拝し、自身の目的のために彼を味方に引き入れようとします。
しかし、宿儺は漏瑚を一切相手にせず、その実力差を圧倒的に見せつけます。
漏瑚が全力を出したにもかかわらず、宿儺はほとんど傷を負わず、最後は「開(フーガ)」と呼ばれる強力な炎の術式で漏瑚を焼き尽くし、完膚なきまでに叩きのめしました。
この戦いは、宿儺が他の特級呪霊と比較しても別格の存在であることを明確に示しました。
そこに、伏黒恵が奥の手として呼び出した十種影法術の切り札である「八握剣 異戒神将 魔虚羅」が現れます。
魔虚羅はあらゆる事象に適応する能力を持ち、一度攻撃を受けても次にはその攻撃を無効化してしまうという規格外の式神です。
宿儺は魔虚羅の能力に興味を示し、その「適応」を逆手に取って、自身の術式を応用して調伏することを試みました。
この戦いで、宿儺は渋谷の広範囲を巻き込む「伏魔御厨子」を文字通り「領域展開」し、渋谷の街並みを斬撃で切り刻みます。
この攻撃は、魔虚羅だけでなく、その領域内にいた数多くの一般市民や呪術師たちをも無差別に巻き込み、甚大な被害をもたらしました。
最終的に、宿儺は魔虚羅の適応を上回る圧倒的な手数と、再び「開(フーガ)」の炎の術式を組み合わせることで、ついに魔虚羅を調伏(倒す)することに成功。
この戦いは、宿儺の戦闘センスと術式応用能力の高さ、そして何よりもその破壊規模のすさまじさを突きつけました。
渋谷事変における宿儺の行動は、その後の物語に決定的な影響を与えることとなります。
まず、宿儺の意識が虎杖の肉体で行った行為は、虎杖の精神に深いトラウマと責任を刻み付けました。
これにより虎杖はさらなる苦悩を背負い、自身の存在意義を問い直すことになります。
渋谷事変は、宿儺がただの「強大な呪い」ではなく、自身の快楽のために全てを破壊し尽くす「真の呪いの王」であることを決定づけました。
両面宿儺の術式・能力

ここでは両面宿儺の術式・能力を解説します。
術式:伏魔御厨子(ふくまみづし)
宿儺の根幹をなす術式であり、彼の代名詞とも言える能力で、「生得領域の具現化」であり、その性質は非常に特殊です。
通常の領域展開は、術者の周囲に結界を築き、その内部に必中効果を付与するもの。
しかし、伏魔御厨子には結界がありません。
代わりに、周囲一帯を自身の領域として展開し、その中に必中効果をバラ撒きます。
そのため相手は逃げ場がなくなり、術式効果から逃れることが困難となるのです。
伏魔御厨子内で放たれる必中効果は、主に以下の2種類です。
・捌(はち)
術式の対象(生物、呪霊など)の呪力レベルに応じて、適切な角度と硬度の斬撃を自動で繰り出す効果があります。
相手が強ければ強いほど、より強力な斬撃が放たれるという厄介なものです。
これは、通常の斬撃とは異なり、対象を細胞レベルで解析し、最も効率的にダメージを与えるように調整されると考えられます。
・解(かい)
無機物を対象とした斬撃で、建物や地面など周囲のあらゆるものを寸断します。
捌と同様に対象の硬度に合わせて調整されるため、非常に汎用性が高いです。
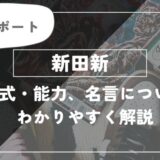 新田新(にったあらた)のサポート術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
新田新(にったあらた)のサポート術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 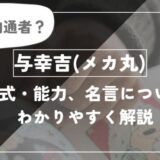 メカ丸(与幸吉)は高専の内通者?術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
メカ丸(与幸吉)は高専の内通者?術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 斬撃術式:斬(ざん)
伏魔御厨子の必中効果の根源にもなっている宿儺の基本術式です。
広範囲を斬り裂く「解」と、対象の呪力を探知し追尾する「捌」が存在します。
これらは通常の呪力操作による斬撃とは一線を画し、対象の強度や呪力レベルに応じた調整ができます。
炎の術式:フーガ(開)
宿儺が領域展開「伏魔御厨子」内で使用した、もう一つの強力な術式です。
彼の口から火柱が放たれる描写があり、その威力は凄まじいことが分かっています。
しかし、この術式の詳細な仕組みや発動条件は未だ不明な点が多いです。
彼の領域内で使用されたことから、伏魔御厨子の必中効果とは異なる独自の術式である可能性が高いと考えられます。
開の意味は、宿儺が「開」と唱えた後に炎を放ったことから、術式の解放を意味するか、あるいは術式の名称そのものである可能性が高いです。
反転術式
呪力を反転させ、負のエネルギーである呪力から正のエネルギーを生み出す術式です。
主に肉体の治癒に使用され、宿儺自身だけでなく他者の治癒も可能であり、その練度は高いとされています。
応用と応用例は以下の通りです。
・治癒能力:致命傷を瞬時に治癒するなど、その回復力は驚異的
・再生能力:失われた身体の一部を再生することも可能
・他者への応用:虎杖の身体を治癒したり、伏黒の魂を安定させたりする描写もあった
呪具の扱いについて
宿儺は、特級呪具である黒閃(こくせん)や八握剣 異戒神将 魔虚羅を自在に操ります。
特に魔虚羅との併用は、彼の戦闘スタイルにさらなる多様性をもたらします。
・黒閃:呪力の衝突により生じる空間の歪みを利用した技で、通常の打撃の2.5倍以上の威力を持つ。
宿儺はこれを極めて高い頻度で発動し、純粋な身体能力と呪力操作の練度の高さを示しています。
・魔虚羅の適応:魔虚羅は、あらゆる現象に適応し、弱点を克服していく式神
宿儺はこれを呼び出し、その適応能力を自身の戦闘に組み込むことで、相手の術式を無効化したり、自身の攻撃を強化したりするなど戦略的な戦い方を展開します。
さらに、強大な呪力量に加え、その呪力を極めて精密に操作する能力を持っています。
これにより、彼の術式は常に最大限の効率で発揮されるのです。
また、相手の術式や動きを瞬時に分析し、適切な対応をとる高い知性も持ち合わせています。
さらに作中では、他者の術式をコピーしたり、その性質を読み解いて利用したりするような描写も見られました。
これは、彼の術式に対する深い理解と、それを自身の戦闘に活かす応用力の高さを示しています。
宿儺の戦闘は、単なる力のゴリ押しではなく、極めて戦略的かつ冷徹なものです。
これらの能力が組み合わされることで、彼はまさに「呪いの王」としての地位を確立しています。
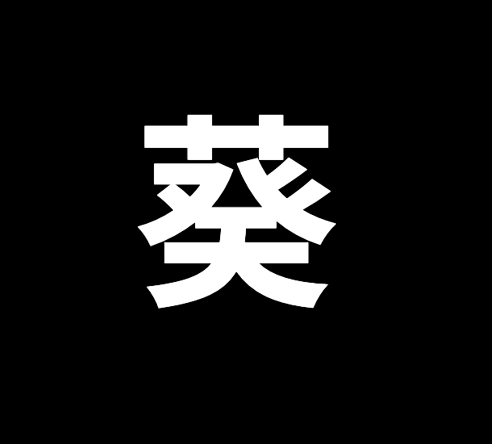
五条悟が認めるほどの強さなんだよね
両面宿儺の印象深い名言・エピソード

宿儺は、一言で言えば「圧倒的な力と残虐性を持つ、呪いの王」です。
作中でもその強大さ、冷酷さ、そして時に見せる知性によって、読者に強烈な印象を与え続けています。
そんな宿儺のセリフやエピソードをいくつか紹介していきます。
- ああやはり、光は生で感じるに限るな
- 全く…いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は
- この虎杖とかいう小僧、一体何者だ…
- 小僧の体をモノにしたら、真っ先に殺してやる
- この俺を完全になめてやがる
- どうすれば、あの小僧を後悔させられるかをな
- 宝の持ち腐れだな
- 許可なく見上げるな、不愉快だ…小僧
- 惨めだなあ この上なく惨めだぞ、小僧
- 共に腹の底から小僧を笑った仲だ、一度は許す
- 大勢の人間を助けるか…小僧、お前がいるから人が死ぬんだよ
- 頭が高いな
- 俺に一撃でも入れられたら…お前らの下についてやる
- これより四方一町の人間全員、俺が「よし」と言うまで動くのを禁ずる
- 寄り合いで自らの価値を計るから、皆弱く、矮小になっていく
- 理想をつかみ取る「飢え」お前にはそれが足りていなかった、だがまあ、多少は楽しめたぞ
- 人間・術師・呪霊、千年前やった中ではマシな方だった 誇れ…お前は強い
- 見せてくれたな、伏黒恵!
冷徹な宿儺らしい、自身の強さに何の疑問も持たない言動が多く見られます。
特に「愉悦」を感じると楽しそうなところがは相手に恐怖を与えています。
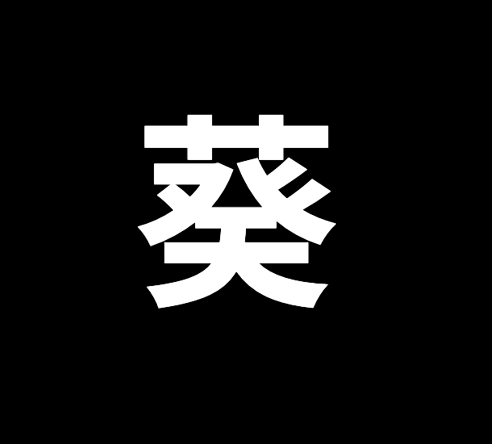
容赦ない残虐性が怖いくらいだよね
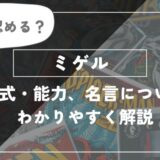 ミゲルはくそ強い!術式・能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
ミゲルはくそ強い!術式・能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 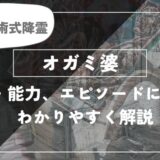 オガミ婆は死亡した?術式や能力・エピソードについてわかりやすく解説【呪術廻戦】
オガミ婆は死亡した?術式や能力・エピソードについてわかりやすく解説【呪術廻戦】 両面宿儺の死と伏黒恵との関わりについての考察

両面宿儺は虎杖だけではなく伏黒にも執着し、「受肉」しています。
宿儺にとって伏黒の術式が、特別な意味を持っていたためです。
宿儺が伏黒に対して特別な興味と執着を見せるのは、物語の初期から示されていました。
彼は単なる強い術師としてではなく、伏黒の持つ術式「十種影法術」に並々ならぬ価値を見出したからです。
「十種影法術」は、十種類の式神を操るだけでなく、異なる式神を組み合わせる「嵌合」や、最強の式神とされる「八握剣 異戒神将 魔虚羅」を調伏する可能性を秘めています。
宿儺は、この術式の無限の可能性、特に魔虚羅の「あらゆる事象への適応能力」に目をつけ、これを自身の支配下に置くことで、より高みを目指そうと考えたのです。
しかも宿儺は、ただ力を求めるだけではなく、自身の退屈を紛らわせる「面白さ」を常に追求しています。
伏黒の術式を巡るプロセスや、伏黒自身の「覚悟」や「選択」が、宿儺にとっては何よりも「面白い」ものとして映っていたようです。
彼の行動には、伏黒を追い詰めて、その真価を引き出そうとする悪意ある期待が含まれています。
虎杖を一時的な器として利用していた宿儺にとって、伏黒はより完全な、あるいは理想的な「器」としての側面も持っていました。
彼の肉体や呪力特性が、自身の膨大な呪力や術式に適合すると見抜いていた可能性も。
物語が進むにつれて、宿儺の伏黒への執着は具体的な行動へと移っていきます。
渋谷事変で宿儺は虎杖の体を一時的に乗っ取り、瀕死の伏黒恵を強制的に受肉させます。
これは、宿儺が伏黒の肉体と術式を自身のものとするための、長年の計画の集大成でした。
伏黒の肉体を乗っ取った宿儺は「十種影法術」を完全に掌握し、自在に操るようになります。
特に、伏黒自身が調伏しきれていなかった魔虚羅を容易に使いこなし、自身の戦闘力を飛躍的に向上させました。
これは、宿儺が伏黒の術式をどれほど高く評価し、その潜在能力を引き出す術を知っていたかを示しています。
宿儺は、伏黒の肉体を乗っ取った後も彼の魂を完全に消滅させることなく、むしろ自身の支配下に置き、利用しようとしました。
しかし、伏黒の魂が宿儺の行動に抵抗する様子が描かれ、二人の間に精神的な攻防が繰り広げられます。
これは、単なる肉体の乗っ取りではなく、伏黒の術式だけでなく、彼の精神性すらも支配しようとする宿儺の徹底した支配欲を表しています。
宿儺と伏黒の関係は、「圧倒的な力を求める者」と「その力を持つが故に利用される者」という構図で描かれ、読者に衝撃を与えました。
そんな両面宿儺は、原作268話で虎杖によって最期を迎えています。
長きにわたる呪術師たちとの熾烈な戦い、そして多くの犠牲を生み出した宿儺の存在に、ついに終止符が打たれたのです。
宿儺は「解」に必中効果を付与すべく、領域展開を発動しました。
これまで彌虚葛籠などの領域対策で必中攻撃を避けていた宿儺でしたが、釘崎野薔薇の共鳴りによって妨害を受け、「解」の直撃を許してしまいます。
そこへ虎杖の猛攻が畳み掛けられ、黒閃まで喰らってしまったのです。
その結果、伏黒の身体から引き剥がされ、依代を失った宿儺は完全に弱っており戦闘不能に陥りました。
虎杖はそんな宿儺に、自分との共存を提案しますが、宿儺はこれを拒否。
宿儺は呪いとしての生を全うする道を選び、虎杖の手中でその存在を終えました。
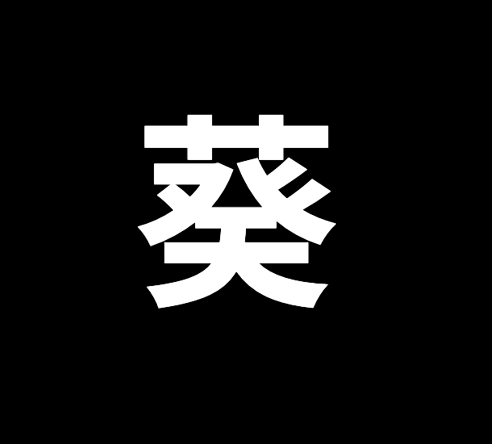
ずっと伏黒を狙っていたんだね
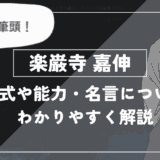 楽巌寺嘉伸の術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
楽巌寺嘉伸の術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 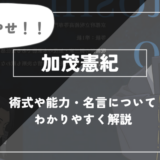 加茂憲紀の術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】
加茂憲紀の術式や能力・名言についてわかりやすく解説【呪術廻戦】 両面宿儺に関するよくある疑問・共感ポイント

両面宿儺の本当の姿
宿儺は「生前宿儺」とも呼ばれています。
彼の生前の強さは、現代の特級呪術師ですら比較にならないほど規格外でした。
どれほどの術師が挑んでも彼を止めることはできず、その存在はまさに「災害そのもの」だったのです。
作中で宿儺が真の力を解放した際に現れる四本の腕と二つの顔という異形の姿は、まさに生前の彼が到達した境地、あるいはその強大さの象徴です。
この姿は、渋谷事変編の真っ最中に掲載されたセンターカラーで初めて公開されました。
その後、死滅回游編における仙台結界での戦いが終わった直後の、烏鷺亨子の回想シーンで再び登場しています。
平安時代の宿儺は人間でありながらも、その圧倒的な呪力と呪いの力によって、このような異形の肉体に変貌したと考えられます。
これは、彼が純粋な人間としての限界を超え、呪いの概念と一体化した結果である可能性があるからです。
自らの呪術を最大限に引き出すために、自身の肉体を改造した結果と見ることもできます。
『呪術廻戦』に限らず、古代において強大な力を持つ者は、しばしば神や鬼のような姿で描かれることがあります。
宿儺の異形もまた、彼がどれほど人々に恐れられ、神話的な存在として認識されていたかを示しているのです。
生前の宿儺は、自身の根幹をなす術式である「伏魔御厨子」を完成させていたと考えられます。
現代においてもその強力さは健在ですが、生前の彼はこの術式を最大限に、そして躊躇なく使用していたのでしょう。
宿儺の強大さは、彼の死後も終わることはありませんでした。
彼の肉体の一部である20本の指が特級呪物として残り、現代に至るまで呪力を放ち続けていたのです。
これは、彼の存在そのものが呪いとなり、千年経ってもなお世界に影響を及ぼし続けるという、まさに「呪いの王」たる所以です。
生前の宿儺は、自身の死後も影響力を持ち続けることを望んでいたのか、あるいは単にその存在があまりにも強大で、完全に消滅させることが不可能であったのかは不明です。
しかし、彼の指が現代の物語の始まりとなり、虎杖、そして伏黒といったキーパーソンたちの運命を大きく変えるきっかけとなったことは間違いありません。
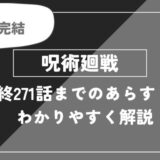 呪術廻戦の最終271話(全巻)までのあらすじをわかりやすく解説
呪術廻戦の最終271話(全巻)までのあらすじをわかりやすく解説 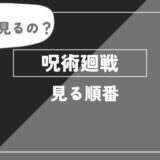 アニメ「呪術廻戦」を見る順番まとめ
アニメ「呪術廻戦」を見る順番まとめ 両面宿儺と五条悟との戦い
呪術廻戦における両面宿儺と五条悟の戦いは、まさに「現代最強」と「呪いの王」による頂上決戦です。
この戦いは、長らく封印されていた五条が解放され、宿儺が伏黒の肉体を乗っ取ったことで必然的に訪れました。
五条は現代最強の呪術師として宿儺という特級呪霊の脅威を排除する義務を、そして宿儺は自身の邪魔となる五条を排除し、自由を謳歌するために戦ったのです。
戦いは、五条悟の「無量空処」と「伏魔御厨子」の応酬から幕を開けます。
両者の領域展開は、互いに相殺し合う、あるいは領域内で激しくぶつかり合うという異例の展開を見せました。
特に、宿儺の「結界を持たない領域」は五条を驚かせ、領域勝負の新たな次元を示しています。
領域の展開と解除、再展開を繰り返す中で両者は互いの術式や呪力残量を探り合い、高度な駆け引きを繰り広げました。
領域展開の膠着状態が続くと、戦いはそれぞれの術式と身体能力を駆使した激しい肉弾戦へと移行します。
五条は「無下限呪術」を、宿儺は「斬撃と魔虚羅」を使い、凄まじい戦いとなっていきます。
宿儺は魔虚羅を盾にしたり、五条の攻撃に適応させたりすることで、五条の術式を攻略しようと試みました。
五条もまた、魔虚羅の適応が進む前に決着をつけようと、より強力な「虚式『茈』」を放つなど、互いに限界を超えた力を出し合います。
戦いは、魔虚羅の適応が完了し、五条の「無限」を突破する斬撃が放たれたことで、決定的な転換点を迎えます。
魔虚羅が五条の「無限」に適応したことで、「空間そのもの」を断ち切る斬撃を放つことを可能にした宿儺。
これは五条の「無限」の防御を無視し文字通り彼を両断するという、絶望的な一撃でした。
そして読者の予想を裏切り、五条悟は宿儺の一撃によって、壮絶な死を遂げます。
現代最強の術師が敗北するという結末は多くの読者に衝撃を与え、宿儺の「呪いの王」としての格を改めて知らしめることになったのです。
しかしこの戦いは、単なる強さの比較に留まりません。
五条は現代の呪術師として最も恵まれた才能を持ち、術式を極めました。
しかし宿儺は、平安時代という呪術全盛期を生き抜き、呪いの王として君臨した「規格外の存在」です。
この戦いは現代の到達点と、過去の絶対的強者のどちらが上回るのかというテーマを提示しました。
そして、五条の敗北は呪術界にとって大きな転換点となることが伺えます。
彼の存在が抑止力となっていた均衡が崩れ、宿儺の脅威がより現実的なものとして立ちはだかることになるからです。
虎杖をはじめとする登場人物たちにとって五条の死は計り知れない衝撃を与え、彼らが宿儺とどう向き合っていくのかを考える出来事となりました。
両面宿儺を演じた声優は?
両面宿儺を演じたのは、諏訪部順一さんです。
プロフィール
生年月日: 1972年3月29日
出身地: 東京都
血液型: A型
身長:173cm
事務所:東京俳優生活協同組合
代表作
- 黒執事(葬儀屋・アンダーテイカー)
- 夏目友人帳(的場静司)
- 坂道のアポロン(桂木淳一)
- 黒子のバスケ(青峰大輝)
- 有頂天家族(下鴨矢一郎)
- ばらかもん(川藤鷹生)
- 文豪ストレイドッグス(織田作之助)
- バチカン奇跡調査官(ロベルト・ニコラス)
- 怪物事変(隠神鼓八千)
- ブルーロック(馬狼照英)
- マイホームヒーロー(鳥栖哲雄)
- 葬送のフリーレン(リュグナー)
- 天久鷹央の推理カルテ(成瀬隆哉)
- まったく最近の探偵ときたら(名雲桂一郎) ほか
諏訪部順一さんは、クールな二枚目からコミカルなキャラクター、シリアスな役柄まで、非常に幅広いジャンルのキャラクターを演じ分けます。
単に声を当てるだけでなく、キャラクターの内面や背景を深く理解し、声色、トーン、間の取り方などで繊細に表現することで、視聴者に強い印象を与えています。
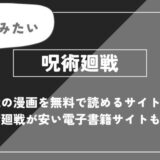 呪術廻戦は全巻無料で読める?安い電子書籍サイトも紹介
呪術廻戦は全巻無料で読める?安い電子書籍サイトも紹介 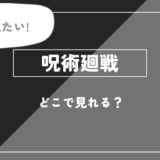 「呪術廻戦」のアニメ全話を視聴できる動画配信サブスクを全て比較
「呪術廻戦」のアニメ全話を視聴できる動画配信サブスクを全て比較 まとめ

今回は両面宿儺について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
両面宿儺というキャラクターは、まさに「呪いの王」の名にふさわしい存在感を放ち、読者に強烈な印象を残しました。
五条を亡き者にしたものの、虎杖たちとの壮絶な戦いで死を迎えてしまいます。
彼の存在が呪術廻戦の世界をより深く、より魅力的にしていたことは間違いないでしょう。
機会があったら、宿儺の生き様をもう1度見返してみるのもいいかもしれません。
\ 推し活におすすめの「推し」サービス /
| 電子書籍 | VOD | フィギュア/グッズ通販 |
|---|---|---|
30日間無料 コミック.jp |  初月無料 dアニメストア |  1万円以上購入で送料無料 ホビーストック |
 6回分クーポン ebookjapan |  580円/月 ABEMA |  最大76%OFF あみあみ |
 50%還元 Amebaマンガ |  初月無料 PrimeVideo |  充実な品揃え キャラアニ.com |
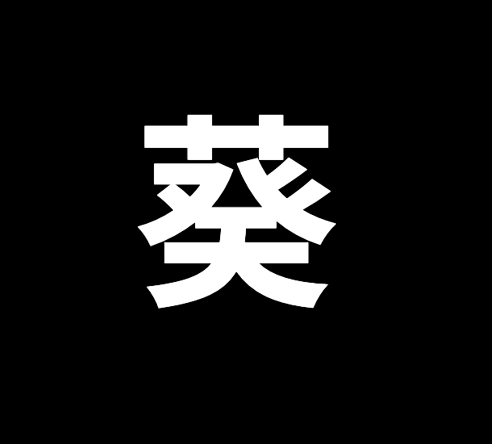
とりあえず、安いのまとめてみました!
一緒に推し活楽しみましょう…(以下より本編)